まだ『 TENET 』シリーズを続けるわけだが、前回の記事を確認すると、“十一曜紋” のところらへんで終わってる。
この “十一曜紋” の部分に関しては、『日月神示』や『火水伝文』を読み込んでいる人がいれば、それなりにピンッ!とくるはずだと思うのだが、いかがなものか。
富士は晴れたり、日本晴れ。かみ(◯にゝ)の国のまことのかみ(◯にゝ)の力をあらわす代(よ)となれる。
ご存じ、『日月神示』「上(うえ)つ巻」第一帖の冒頭だ。
「富士」は「二二」である。
*
『 TENET 』に戻るが、セイターがあろうことか自分の妻キャットを撃ち、キャットの治療もあり、主人公とニールとキャットは逆行するコンテナに乗り込むことになるが、そのときの会話で主人公がニールに、「われわれは未来人の先祖になるわけだから、先祖を殺せば自分たちを殺すことにならないか?」と聞く場面があるが、ニールは、それは「パラドックスだ」と言う。
いわゆる “祖父殺しのパラドックス” ってやつだが、そりゃその通りで、もしおじいちゃんを殺せば自分は生まれないことになり、だとすれば、おじいちゃんを殺しにくることもできないわけだから、そもそも “祖父殺し” ということ自体が成り立たない。
だから、もし祖父を殺しても自分に影響がないとすれば、自分の時間軸と祖父の時間軸は同じ時空を共有していないという前提が必要になる。
そしてそれとは別に、『 TENET 』の未来人はニールに言わせると、祖先に何をしても自分たちには影響はないというか、どうでもいいと考えているようなのだ。
それを聞いた主人公が、「彼らは正しいのか?」と問うと、ニールは「関係ない。彼らはそう “信じている” 」と言う。
さらに主人公が、でも、われわれがこうしていられるってことは、彼らを阻止したということじゃないのか?みたいなことを言うと、ニールは「楽観的に見ればそうだ」と答える。
「悲観的には?」と主人公。
するとニールは、「パラレルワールド理論では、われわれは “意識と多元的現実との関係” は知り得ないのだ」と言う。
ここでも、重要なテーマが提起されている。
つまり、“時間軸は一つである” ということだ。
ノーラン監督も『 TENET 』に関するインタビューで「時間軸は一つだ」と言っている。
『 TENET 』の時間軸はあくまでも一つであり、登場人物たちは一つの時間軸の過去と未来を行き来しているのだ。
だから、当たり前だが、過去に行けばそこには過去の自分がいる。
そして、自分同士が生身の身体で接触すると対消滅を起こすとされている。
よく SF 小説に出てくる物質と反物質の関係だろう。
そういう意味では、『 TENET 』は “タキオン粒子” の話にも関連し、いわゆる虚数の質量を持つ粒子で構成される場、“タキオン場” にも触れなきゃならないのだろうが、私の手には余るし、どこかで専門家がきちんと解説してるだろうから、ここでは言及しない。
ひとつだけ言っとけば、タキオン粒子は光速を超える粒子として理論上知られているが、光速を超えているだけに、超光速物体はわれわれの目の前を通りすぎても目には見えないが、やがて互いに反対方向へ向かう二つの像として見えるというよくわからない性質があるが、実はまさに『 TENET 』の時間における “中間地点” にいるときのような話でもある。
このシリーズの最初に触れたが、スタルスク 12 の戦場で、順行組と逆行組が 10 分間の中間地点、5 分経過の地点で同時に同じビルを砲撃するシーンがあるが、そのときの現象が先のタキオン粒子の “見え方” のヒントになるかもしれない。
話を戻すが、パラレルワールド理論に関していえば、仮にそういう世界があったとしても、それを経験するのは自分の意識なので、どこまで行っても時間軸は一つである。
時間の流れが早いと感じる世界でも、あるいは時間が止まってる世界だとしても、それに気がつくのは自分の意識だ。
あえて “自分” の意識と言っているが、“あなた” の意識と “あの人” の意識とを区別するためである。
“自分” には “あなた” の意識も “あの人” の意識も意識しえない。
想像、推測することはできるかもしれないが、意識そのものにはならない。
しかし、“自分” と “あなた” と “あの人” の意識の区別がなくなったときは話が別だ。
そのときは、あえて “自分” の意識という必要もなくなり、ただの “意識” でいいだろうが、それでも “自分” の意識と言うならば、すべては自分ということになる。
ここには、非常に “あぶない” 罠のような回路があり、『ラー文書』でいえば、オリオングループの “自己奉仕” とワンダラー系の “他者奉仕” の概念とも絡み、さらに上位の概念ともいうべき “一なるもの” の理解も必須となり、もっといえば、ラーすらも理解していないかもしれないさらなる上位概念があり、それは日本と関係してくるのである。
しかし、いくらなんでもすっ飛びすぎなので、話を戻せば、いずれにしろ時間軸は一つになるということだ。
時間とは、意識と現実との関係の問題である。
*
ノーラン監督に『メメント』という映画があるが、あれも “記憶” にまつわる映画で、やはり意識と現実の関係がテーマとなっている。
というか、『メメント』の冒頭のシーンはまんま『 TENET 』といってもよく、あ、これもネタバレだが、冒頭のシーンは物語のエンディングであり、そこから映画がスタートするわけだが、オープニングのポラロイドで撮った写真を手で振って乾かすシーンでは、だんだんと写真に画像が浮かび上がってくると思いきや、実はどんどんと薄くなっていっていることがわかり、そのうち写真がポラロイドカメラにするっと戻り、主人公のガイ・ピアースの手に捨てたとおぼしきピストルが飛び込んできて、倒れていた男がゆらりと起き上がり、落ちてた薬きょうが銃に戻り、発射する……そう、つまり、『 TENET 』の逆行シーンとまったく同じ映像からはじまるのである。
で、映画はカラー映像とモノクロ映像が入れ子となって展開していくが、カラー映像は現実の時間軸、といっても大きな流れは逆行しており、いくつかの場面に区切られた映像が、区切られた時間内では順行で進んでいくが、区切られた場面場面は過去に遡っていく。
そしてモノクロ映像はどうやら主人公の記憶のシーンであり、それは過去から未来へと順行で進んでいく。
そして『 TENET 』じゃないが、物語のモノクロシーン、つまり主人公レナードの記憶の映像のある地点から、それはある男を殺害し、ポラロイドで撮影したフィルムを冒頭シーンのようにまた手で振っているシーンなのだが、そのフィルム画像がだんだんとクリアになっていくにしたがって、映像もモノクロからカラーになっていき、そこから映画の現実のシーンとして展開していくという構成になっている。
つまり、この映画は主人公がひとりの男 A を殺したところからはじまり、また別の男 B を殺すまでの物語なのだが、映画の構成としては、男 B が殺されたところから時間が逆行し、男 A が殺害されるところで、モノクロの順行の記憶と逆行してきた現実の時間が一致し、そこで時間がある意味反転し、映画の観客にとっては、事件によってわずかの間しか記憶できなくなった主人公のモノクロの順行記憶と、実際に進行している現実の逆行時間がその地点で融合するという具合になっている。
そして映画としては、主人公レナードの人生は、男 AB が今後は新たな CD となり、また別の EF となっていき、これからも同じことを繰り返していくのだろうと暗示させて終了する。
しかしもっとも重要なことは、主人公はその繰り返し、その円環構造のループの中に入っていくことを自ら選択した、ということなのである。
気の毒な記憶障害を負ってるとはいえ、うすうす真実に気づきはじめている自分に気づきながらも、レナードはそれと直面することをなぜか避け、自分の記憶障害を利用してある種の自己韜晦を企てることで、主人公は文字通り命脈を保っていく。
ところで映画では、それとは別に主人公の記憶障害を利用する輩が 3 人登場し、ひとりはレナードから宿泊費を余計にふんだくるモーテルのあんちゃんであり、これはまあ、ケチなこそ泥みたいなものだが、もうひとりは麻薬の潜入捜査中の刑事ジョン・ギャメル、別名テディで、テディはレナードを利用して、ヤクの売人たちの麻薬取引の金を横取りしようとたくらんでいる。
そして最後のひとりは、そのヤクの売人ジミーの恋人のトリニティーじゃなくてナタリーで、キャリー・アン・モスが演じているのだが、ジミーがドットという男の大金を持ったまま行方不明になっており、ナタリーはドットに金を横取りされたと疑われて命を狙われてるので、レナードを利用してドットを始末させようとしている。
モーテルのあんちゃんもテディもナタリーも、レナードが記憶障害であることをいいことに、当たり前だが断然優位な立場に立っているわけだが、この構図はなんとなく、自分たちの支配下におくために、地球人の意識をある領域に閉じ込めたままにしておく不逞な輩たち(地球外知的生命体)、といったものとも似てなくもない……
*
ちなみに、主人公レナード通称レニーは、自分の妻を殺した犯人を探し出して、復讐することだけを生きる目的としているわけだが、その犯人の名は、自分の体に入れ墨で彫り込まれた「ジョン・G 」ということになっている。
そして、ヤクの売人ジミー・グランスや、麻薬捜査官ジョン・ギャメル別名テディを殺すことになるが、うがったことを言えば、このジョン・G とはヨハネとゴッド、つまり預言者と神の象徴とも思われ、となれば主人公レナードは預言者と神探しをしていると同時に、預言者と神殺しをしているということにもなる。
ここでジョン・G と聞くと、どうしてもアイン・ランドの小説『肩をすくめるアトラス(アトラス・シュラッグド)』を思い出さずにはいられないが、これは映画化もされており、たしか3部作で、私は 2 作までしか観てない。
内容は近未来っぽいアメリカの姿であり、超国家社会主義的な世界のもとでアメリカの企業と統制国家との闘いのようなことが描かれ、ディストピアともユートピアともいえないというか、やはりディストピア的なのだろうが、国家を超えて自分たちの共同体を創っていくとかいないとか、そんな物語だ。
そこで、キーワードとして「ジョン・ゴールトとは誰だ?」( Who is John Galt?)というフレーズが頻繁に出てくるのだが、どうもその理想とされる共同体を率いるリーダー的な存在の名前らしく、というか、ジョン・ゴールトという名がその共同体を創るといった思想自体の象徴にもなっていき、中盤からしばらく、そのジョン・ゴールトは何者かを巡る物語となったと記憶している。
ジョン・ゴールト、つまりジョン・G だ。
こうしたときの「ジョン・ゴールト」や「ジョン・G 」といった “もの” は、『 TENET 』に出てくる “アルゴリズム” のようなものでもあり、確固たる規範というか形式として存在してきたかに見える既存のパラダイムを、一気に転覆させる力を内在させているわけだ。
いや、なんだかとんでもなく遠いところに来てしまった気がしないでもないが、そんなことはなく、何が言いたいかというと、『メメント』に出てくる「ジョン・G 」から『肩をすくめるアトラス』を思い出したわけだが、『肩をすくめるアトラス』が持つある種のやりきれなさというか、どこか沈鬱な雰囲気が、『メメント』にも多少漂っているような気がするのだが、それは『肩をすくめるアトラス』の原作者であるアイン・ランドの思想、つまりオブジェクティビズムに由来するのだろうと思うわけだ。
オブジェクティビズムとは客観主義といわれるが、簡単に言えば、意識と現実は分離しているということである。
意識とは別個に現実というものが存在しており、意識は感覚を通して現実を知覚するだけであり、現実と接触した知覚を通して現われるときに意識は意識となるのであって、意識自体は自らを意識と認識することはできないというか、早い話が、独立した意識なんてものはないとする思想である。
『メメント』の主人公レナードもラストシーンで、車を運転しながら心の中でこうつぶやく。
I have to believe in the world outside my own mind.
自分の意識の外側に世界はあるはずだ。
I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember them.
たとえ忘れたとしても、自分のしたことにはきっと意味がある。
I have to believe that when my eyes are closed, the world's still there.
目を閉じても、そこに世界はあるはずだ。
そう思って、レナードは運転しながら目を閉じる。
But do I? Do I believe the world's still there?
本当か? 本当に世界はあるのか?
Is it still out there?
まだ、そこに?
レナードが目を開ける。
Yes.
あった。
We all need mirrors to remind ourselves who we are.
記憶は自分の確認のためにあるのだ。
I'm no different.
みんなそうだ。
「 We all need mirrors to remind ourselves who we are 」とは、確かに先の訳のような意味なのだが、そしてここだけ字幕の訳にしたが、ヘタな直訳・意訳をすれば、「われわれは自分が何者かを知るためには、自分自身を映し出してくれる鏡のような存在を必要とするのである」ということだろう。
つまり、オブジェクティビズムそのものではないだろうか。
自分の外部に実体があり、われわれはその実体を感覚で知覚することによって意識に上らせ、その意識によって相対的に “自分” というものを知るということだからだ。
レナードのように数分後に記憶が消滅する人間にとっては、事件で記憶障害を起こす以前の自分の記憶はありながら、事件後の記憶は常に現在から数分前までしかないので、自分はなんのために今の行動を起こしているのか、どういう理由でこれをしているのか、まったくわからない。
そんな人間が生きていくためには、今、自分のしていることにはきっと意味があると信じるしかない。
たとえ理由がわからなくてもだ。
そしてレナードは、他人にいいように利用されるかもしれない人生ではなく、たとえ間違っていようとも、他人との関係を、世界との関係を、自分が描いたシナリオどおりに生きようとするのである。
ここに至って、初めてレナード独自の “主体性” が立ち上がってくるわけだが、それは先にも書いたが、直面したくないある真実を回避する形で行なわれることになるので、レナードのそうした欺瞞性や不安定性が、映画全体に薄もやのように陰鬱さを漂わせることになるが、それは根本的には、レナード自身のオブジェクティビズムに端を発しているのだ。
てか、ここまで『メメント』に触れるつもりはなかったのだが、『 TENET 』の主人公においては、レナードとはまったく違う意味で “主体性” を獲得しており、ラストでさらに新たなポジションを確立させるという物語であることを言いたかったのである。
続く

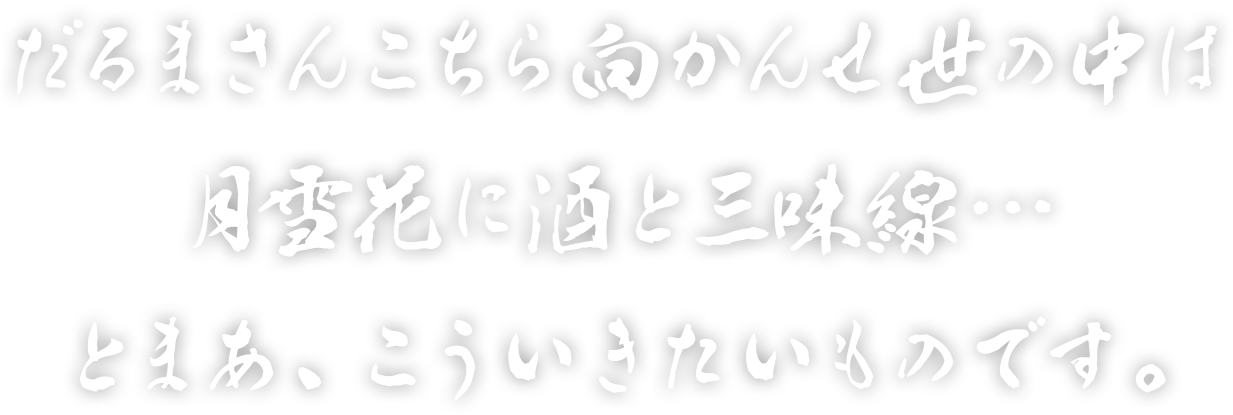
Commentコメント