テレ朝の『ミュージックステーション』を久しぶりに見る。やはり女、子どもが明るく、屈託がなく、元気がいいということはいいことだと思った。当たり前か。女、子どもが暗く、鬱屈していて、元気がないなんて国はロクなもんじゃないだろう。歌と踊りというものは人を元気にする。理性じゃないところに響くからだ。
祭りが原点だね。日本人は祭り好きだし、歌もカラオケなんてものを発明したくらいだから絶対好きだ。
祭りといえば踊りだが、踊りといえば、いきなりアーサー・C・クラークの『幼年期の終わり』を思い出した。
幼年期の終わりとは、地球の幼年期の終わりという意味だ。ある日、空に巨大な UFO 軍団が現れて、戦争ばかりしていた地球を管理し始める。不正、独裁、その他あらゆる地球上の悪を駆逐する。UFO 軍団の連中はどこかの星の知的生命体で、超高度な科学技術を持っている。上主と呼ばれる者がトップにいるが、その正体は誰も見たことがない。そもそもこの UFO 軍団の目的もよくわからない。地球を管理してどうしようというのか。最後にこの上主の正体が垣間見られるのだが、ネタバレになるとまずいので伏せておく。ともかく、地球の最後の時期、新しく生まれてきた人間たちは、皆一心不乱に踊り出すのだ。ジャングルの中でもどこでも、体が傷つこうがどうしようがおかまいなしに踊り続ける。その描写はちょっと怖かった記憶がある。
三島由紀夫はこの小説をたしか一番恐れていたはずだ。本当に恐ろしい、というようなことをどこかで書いている。私もこの小説はあまり好きではなかった。なんともやりきれない、というか、後味があまりよくなかったと思う。でも傑作であることには違いない。クラークには『 2001 年宇宙の旅』もそうだが、どこか予言者めいたところがある。クラークに限らず、H・G・ウェルズでもコナン・ドイルでも、イギリスの( SF )作家はどこか神秘的だ。ドイルは英国心霊現象研究協会に関わっていたはずだ。クラークも心霊現象を否定していないし、彼らのような作家はどこか無意識でアカシックから情報を得て書いているんじゃないかと思いたくなるようなところがある。たしか、夜空はなぜ暗いのか、といった歴史的な難問も、アメリカのミステリー作家エドガー・アラン・ポーがすでに解いていたはずだ。宇宙には何千億も星があるのだから、本当は夜空は明るくなければいけない。いろんな説が登場したが、ポーがどこかのエッセイで、夜空に暗い部分があるのは、その先にある星が遠すぎてまだ地球にその光が届いていないからだ、と書いていて、それが実際に 20 世紀になって証明された。やはり、既成概念にとらわれない人間の自由な発想、想像力の中にだけ多くの可能性が隠されているということか。
話がすぐとっちらかるが、先の『幼年期の終わり』は一種の終末論だが、どうもある種の真実を含んでいるようで怖い、ということがいいたかったのである。地球の成長、あるいは今取りざたされているアセンションにまで思いが及ぶような内容を、なぜ 50 年代にクラークが書けたのか。まあ、天才だからだということにしておこうか。
三島が怖がったとも書いたが、三島由紀夫は『美しい星』というSFもどきの小説を書いていたとき、自らリュックを背負って埼玉の山にUFOを見に出かけるような人だから、なにか感性的に共鳴するものがあったのだろう。三島で思い出したが(こればっかだ)、誰だったか、三島の晩年、外国人の知人が三島邸を訪れたのだが、その外国人の知人が三島になにを話しかけても三島は上の空で、日本は終わりだ…日本は首もとを緑色の蛇に噛みつかれていて、もうどうすることもできない…というようなことをぶつぶつとつぶやくだけだった。三島の自決後、その外国人がどこかの雑誌でそう回顧しているのを読んだことがある。緑色の蛇とはいったいなにか? 私はその後その話は忘れていたが、6、7年前、『文芸春秋』でたしか文春の元編集長だったかの人がその話を取り上げていて、緑色の蛇は米ドルだ、といっていた。たしかに米ドル札は緑色だ。その人は、日本は戦争でアメリカに負け、その後さらに経済的にもアメリカに支配されていて、三島はそれを知って絶望したのだ、というようなことをいいたかったのだろう。
そのとき、私は何気に三島のいう緑色の蛇とは、フリーメーソン、イルミナティと関係があるように感じた。万物を見通す目の下の十字架に巻き付いているのは緑色の蛇だし、フリーメーソンと緑色と蛇の連関は探せばいくらでも出てくる。皇室がフリーメーソンと関係していることはよく話題になる。三島はなにを知って絶望したのだろうか。遺作となる4部作『豊饒の海』の「天人五衰」にもそれらしき描写が出てくる。世界には超金持ちがいて我々を牛耳っている。彼らは美しくて純真なものが嫌いで、そうしたものを破壊してまわる。そしてついに日本にまで手を伸ばしてきた。我々は彼らには勝てない。なぜなら、美しくて純真な者は少数で、世の中の大半は彼ら金持ちのほうにつくからだ。だから、我々は密かに自尊心を保ちつつ、彼らに屈服しているふりをする必要がある。そして彼らの弱点を虎視眈々と探し、いつの日か立ち上がるのだ、といった内容だったと思う。まるで、『日月神示』みたいではないか。
緑といえば、最近中沢新一が立ち上げた『 GREEN ACTIVE 』もそうだが、本来はエコ的なクリーンなイメージがあるはずだが、反面、江戸川乱歩の『緑衣の鬼』のように、ちょっと怖いものとも結びついている。その本の中にも、緑色はキ印の色だ、といった表現があったと思う。キじるしってなんだ?と思って、当時子どもだった私は母親に聞いた覚えがある。すると母親は、キチガイのことだよ、といった。今じゃ、ピー言葉だろうが、当時は普通に使っていた。緑といえば、小島信夫のあれはなんだったか、『寓話』だったかな、緑色のことがちょっと出てきて、モンドリアンだったかモディリアニだったか(モしかあってない!)、ともかくどちらかの画家が晩年に緑色を徹底的に嫌ったというエピソードが紹介されていた。緑色が嫌いなので、座るときには窓から緑の木が見えないように座ったというからすごい。もちろん絵にも緑は絶対使わない。そして小島信夫はその話を聞いて、本当にびっくりしたというのだ。それだけ。なぜびっくりしたのか書いていない。
私は、小島信夫がなぜその話を知って心底びっくりしたのかが気になってしょうがないのだが、最近故人になられたから直接本人に聞くわけにもいかない。誰か知りませんかね?
フリーメーソン、イルミナティの儀式に関しては、『地球を支配するブルーブラッド 爬虫類人DNAの系譜』に詳しく書いてある。もとその儀式に参加していた著者によるある種の告発本なので、そのリアリティは迫力がある、というか心臓が弱い人はあまり読まないほうがいいかもしれない。真実であるかどうかはともかく、人間のタイプによっては知らなくてもいいということがあるのかもしれないし。この本は、人類誕生の話もそうだが、本当に驚くようなことばかりで、おそらく世の中的にはトンデモ本として片づけられているのではないだろうか。そういえば爬虫類人も緑色らしい。

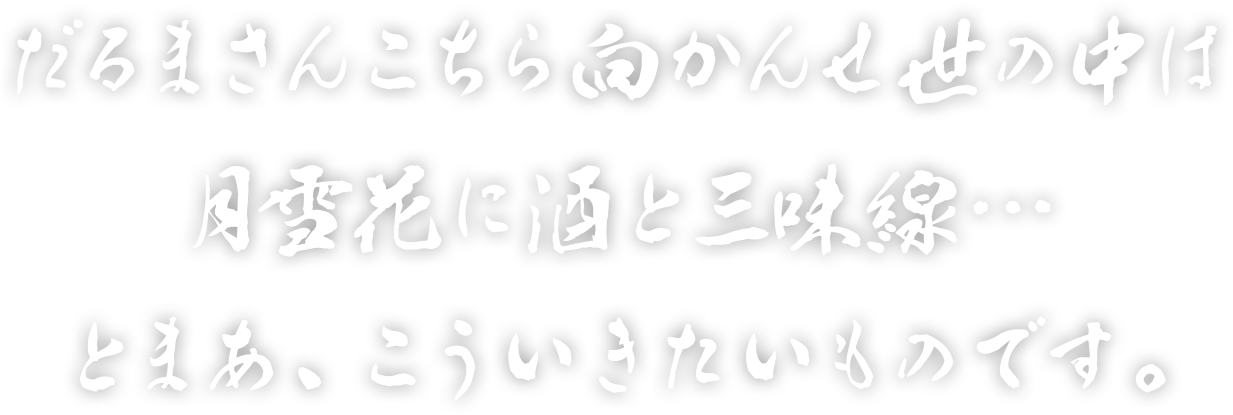
Commentコメント