よくまあ毎日飲んでると自分でもあきれる。打ち合わせだ食事会だと言ってはいるが、やはり飲む。打ち合わせは毎回しっかりやるし新企画や新しい人脈にも必ず繋がるのだが、飲む。これは外国人とも同じだね。といっても最近はアジア人とばかり会っているが。体がもたないときもあるし、よく人からは、ご自愛を、といわれる。よほど心配されるような飲み方なのだろう。でもまあ、私は15歳から飲んでいるから今さらジローだし、死んだ親父も毎晩欠かさず大酒かっくらっていたが肝臓はなんともなかったという人間だから、自分もそうなのかもしれない。飲んでるほうが調子がいいくらいだ。そういえば新宿の G 街で西部邁氏と同席したとき酔っぱらいの話になって、西部氏は、人間酔っぱらってるくらいがちょうどいい、そりゃ時には間違いもあるだろうが、酒はやがて醒める、すると反省する、反省したぶんだけ進歩する、現実は永遠に醒めない悪夢のようなもので・・・などと言っていたのを思い出す。西部先生、私はもう 30 年以上もちょうどよく生きてきたんですかねえ。
昨夜はバカボン山田さんたちと軽いオフ会&打ち合わせ。話は尽きず、あっという間に時が経った。いろいろ始動し出したって感じ。帰って家でケーブルテレビをつけたら『空の大怪獣ラドン』をやってて、ありゃと。ちょっと前にこのブログのコメント欄でラドンの名が出たこともあり、そのまま観てしまった。
1956 年だって。終戦から10年でこういう映画を作ったというのも何だかすごい気がしてきた。東映初の総天然色映画というのも力が入ってないか、怪獣映画だぞ。東宝のゴジラから始まってラドンにモスラ、ガメラにギャオスにキングギドラときたもんだ。小学生時は何とも思わず夢中で見てたが、ウルトラマンにしてもセブンにしても、日本の怪獣ものはやっぱり大したものなんじゃないか。怪獣も何とか星人もいろいろ悪さをするのだが、そして最後は正義の味方にやっつけられて死んじゃったり逃げたりするのだが、どこか一抹の哀しさがあるような・・・。ラドンだって最後は溶岩に焼かれてゆっくりと死んでいくが、それを見ている自衛隊の連中にも悲しみの表情があったような・・・。ゴジラにしたって人類が作った核のせいで生まれたわけだろう? 生まれてはみたもののまた人類によってやっつけられる。うーむ、ゴジラの立場は。
でも特撮ものの原点はやっぱりアメリカのキングコングだろう。円谷英二があれを観て特撮の監督を目指したってくらいだからね。さすがアメリカ、ああいう大ナタ振ったようなエンターテインメントはうまいというかスケールがでかいというか。キングコングは 1933 年。日本人も度肝を抜かれたんだろうな。何でも、あの怪物は本当にいるのかと問い合わせが殺到したというから、かなりの影響を受けたでしょう。
影響といえば、日本の黒澤明や小津安二郎たちの映画の世界への影響は言うまでもないが、ユル・ブリンナーやスティーブ・マックイーン、ジェームス・コバーンが出た『荒野の七人』という映画は子ども心によく覚えている。黒澤の『七人の侍』のリメイク。横行している強盗団の村の略奪から貧しい村人たちを守るために七人の男たちが安い報酬で用心棒となる話だ。話も面白いが、印象に残ったのは、その中のひとりが死ぬ場面。そいつは、そんな安い報酬( 20 ドル)でこんな仕事を引き受けるヤツがいるわけがない、何か裏があると勘ぐっていて、ユル・ブリンナーたちや村人に聞いて回っている。そんなものはないと言っても、まあいい、とか言って訳知り顔でニヤニヤしている。最後、撃たれて死ぬのだが、死ぬ間際ユル・ブリンナーに介抱されながら、最後に本当の目的を教えてくれと言う。ユル・ブリンナーはちょっとの間考えていたが、金(きん)だ、という。そいつは、やっぱりなというふうにニヤっとして、いくらだ?と聞く。ユル・ブリンナーは 50 万ドルでひとり7万ドルだと言う。そいつは心底嬉しそうな顔をして死んでいく。うろ覚えだがそんな感じだった。そのシーンが妙に印象に残った。
ユル・ブリンナーはなぜ嘘を言ったのか。死んだあいつは何で安い報酬の仕事が信じられなかったのか。まあ、今となれば理解できるが(当たり前だ、いい歳なんだから)、当時の私にはよくわからなかった。というか、ユル・ブリンナーが相手を思って嘘を言う気持ちはなんとなくわかったが、そいつが金づくでしかものを考えないという感じがわかりにくかった。他の六人たちの内面は、日本の映画というか日本にある物語の流れとしてはわりとわかりやすいものだ。でも当時のアメリカ人たちにとっては、あえて原作にはないあのシーンを入れないと、仕事に意気を感じた他の六人の男たちの心情というのがうまく理解できなかったのではないか。誤解されるとまずいが、アメリカ人が皆、金づくでものを考えていると言ってるのではない。その証拠に、ユル・ブリンナーは黒澤の『七人の侍』を観て感激したわけだから。あれ、ユル・ブリンナーはロシア人だっけ?
私の中ではベスト 3 に入る映画に『無法松の一生』がある。何回観ても最後は涙を禁じ得ないのだがっていうより号泣ものなのだが、『荒野の七人』の話を書いてたら思い出した。『無法松の一生』は戦前の阪東妻三郎主演のものと戦後の三船敏郎主演のものの 2 本が有名だ。阪妻のほうは検閲を受けていくらかカットされたので、監督の稲垣浩が戦後三船版で完全リメイクした。私は両方観ているが、三船版が好きだ。相手の女優が高峰秀子なんだよね。九州小倉の超貧しい車夫、松五郎の話。出自の問題(だろう)で人力車夫になっている松五郎だが、その男気と肝っ玉は世が世ならどれほどの偉業を成し遂げ得ただろう。世話になっていた陸軍の大尉が死んで、その未亡人(高峰秀子)に恋するがじっと胸に秘め、ひとりっ子の敏雄ともども陰に日向に見守っていく。日本映画の傑作のひとつだと思うが、脚本は伊丹万作だ。伊丹万作は日本映画を代表する監督のひとりだが、戦中はいっさい戦争礼賛映画は撮らなかった。本人は病気して撮れなかっただけと言うが、そうではないという説もある。息子の伊丹十三もそのへんに思いがあり、俳優から後に映画監督に転身し、『マルサの女』『ミンボーの女』ほかいろいろ映画を撮った。のではないかと勝手に思っている。伊丹十三にはもっともっと問題作を製作してほしかったが、死んでしまった。
『無法松の一生』には原作があるが、伊丹万作の脚本としてのほうが有名だ。戦争中、中国人たちがこの映画を観て、感激しまくって、日本人というのは一体どういう連中なんだ的なことを言ったという話をどこかで読んだ。
伊丹万作は昭和 21 年というから終戦の翌年、戦争犯罪人を糾弾する団体の発起人に名を連ねていたが、そのいきさつ他、誤解をあらためる文章を『映画春秋』に寄せていて、その人となりがよく出ている。一部抜粋するが、伊丹万作は日本の将来もある種見通していたともいえるかもしれない。
(略)つまりだますものだけでは戦争は起らない。だますものとだまされるものとがそろわなければ戦争は起らないということになると、戦争の責任もまた(たとえ軽重の差はあるにしても)当然両方にあるものと考えるほかはないのである。
そしてだまされたものの罪は、ただ単にだまされたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも雑作なくだまされるほど批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切をゆだねるようになつてしまつた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本体なのである。
このことは、過去の日本が、外国の力なしには封建制度も鎖国制度も独力で打破することができなかつた事実、個人の基本的人権さえも自力でつかみ得なかつた事実とまつたくその本質を等しくするものである。
そして、このことはまた、同時にあのような専横と圧制を支配者にゆるした国民の奴隷根性とも密接につながるものである。
それは少なくとも個人の尊厳の冒涜(ぼうとく)、すなわち自我の放棄であり人間性への裏切りである。また、悪を憤る精神の欠如であり、道徳的無感覚である。ひいては国民大衆、すなわち被支配階級全体に対する不忠である。
我々は、はからずも、いま政治的には一応解放された。しかしいままで、奴隷状態を存続せしめた責任を軍や警察や官僚にのみ負担させて、彼らの跳梁を許した自分たちの罪を真剣に反省しなかつたならば、日本の国民というものは永久に救われるときはないであろう。
「だまされていた」という一語の持つ便利な効果におぼれて、一切の責任から解放された気でいる多くの人人の安易きわまる態度を見るとき、私は日本国民の将来に対して暗澹たる不安を感ぜざるを得ない。
「だまされていた」といつて平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう。いや、現在でもすでに別のうそによつてだまされ始めているにちがいないのである。
一度だまされたら、二度とだまされまいとする真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩するわけはない。この意味から戦犯者の追求ということもむろん重要ではあるが、それ以上に現在の日本に必要なことは、まず国民全体がだまされたということの意味を本当に理解し、だまされるような脆弱(ぜいじやく)な自分というものを解剖し、分析し、徹底的に自己を改造する努力を始めることである。(略)
(『映画春秋』昭和 21 年 8 月号)
何だか話がへんにそれたような気もするが、まあいいか。
これからまた飲みに出ます。18 時に高円寺か・・・

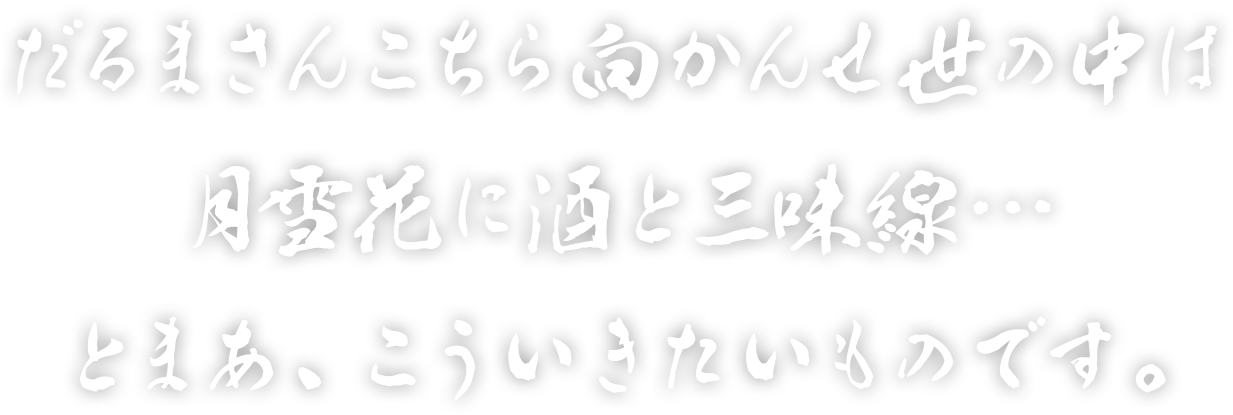
Commentコメント