中野の事務所にもう一週間泊まっている。
いや家は近いのだが、4 駅くらいだが、帰るとすぐ酒飲んじゃうし、いろいろ人もいて、と言っても家族だが、それでも他人は他人なので、ああだこうだと話してると仕事ができない。と言うか、遅くなる。
事務所にいても人がきたりするわけで、しかも中には酒持ってくるヤツもいるから、変わらないと言えば変わらないのだが、要するに泊まると、翌日早くからそのまま仕事にかかれるから効率がいいのだ。
いきなりだが、これからは毎日ブログだけは書こう。あいうえおでも、いろはにほへとでも、ひふみよいむなやでも、何でもいいから書こうと、今なぜか思った。
そういえば、井伏鱒二が NHK のドキュメンタリー番組で、開高健に似たようなことを言っていた。
開高が井伏に、作家も年季が入ってくるといろいろ洗練されてきて、うまく書けるようになるから、初めのころの情熱がなくなる。書きたいという情熱が薄れるみたいなことを言った。どうすればいいのかと。
そしたら井伏が何でもいいからとにかく書けばいいと。まあ、それはそうだけど、あいうえおと書くわけにはいかないと開高が言うと、僕は本当にそう書いたことがあると井伏鱒二が言ったのだ。
確かそんなような話をしていたが、私は、ああ、井伏鱒二なら本当に書いたんだろうなと思った。
私は井伏鱒二をたくさん読んでるわけではないが、すごい作家だと思っている。文章がうまいというか、すごい。情景が目の前に本当に現れてくる。
『荻窪風土記』に作家仲間の外村繁のことを書いた文章がある。外村は小学校の運動会オタクで、まあオタクという言葉は使ってなかったが、運動会見物を道楽にしていたとか何とか、そういう表現だったが、ともかく井伏も同じで、運動会の季節になると近所の小学校をはしごして、見物に出かけていたと。
今じゃ、そんなことをやたらめったらできないわな。不審人物としてマークされてしまう。しかも酒は飲めないんだよな、確か。今は。
まあそれはいいが、だから井伏は行く先々でしょっちゅう外村を見かける。その描写がすごいのだ。ちょっと本を引っ張り出して引用してみる。
(略)外村君が見物するときはよく笑つてゐるので、
遠くから見て大きな口をあけてゐる見物人が外村君だとわかる。
外村君は自分の子供さんの駆けつこを見るわけではなく、
運動会のシーズンに浮かされて闇雲に会場を廻つてゐるやうであつた。
いつ見てもよく笑つてゐるのは、
淋しさとか寂しさなんか癒そさうとしてゐるためではない。
反対に天真爛漫、心から楽しんでゐるやうであつた。
すごくないですか?
運動場の向こうで、外村繁が着流しの袂に両手を突っ込んで腕を組み、大きな口を開けて天真爛漫に笑っている姿が目に浮かびませんか? ということなのである。
何で外村繁のことを書いているのかわからないが、まあ成り行きだ。ともかく、文章の力というものはある。一篇の小説を読むよりも数行の描写がずっと心に残ることがある。
井伏鱒二の『荻窪風土記』には印象に残る話が多くある。あまり辛い話は引用したくないが、作家の小山清の話も書いている。小山の生い立ちもすごく興味深いのだが、それは省く。
とにかく赤貧に陥り、井伏らがいろいろとカンパしたりして支えるのだが、死んでしまう。しかし、小山より早く、奥さんが亡くなる。そのことを書いた箇所を引用する。
(略)それから間もなく小山君の奥さんが自殺した。
「自殺です、睡眠薬をのんで。あのころ分裂症かノイローゼだったんです。
パートで働いてたんですが、朝、洗濯を途中で止(よ)しているんです」
と辻さんは言った。
中央大学の野球グラウンドのすぐ近く、雑木林のなかに倒れていた。
たまたま奥さんの兄さんが来ていたが、
手分けしてさがし当てたときには意識が無くなっていた。
睡眠薬を一瓶まるまるのんだみたいであった。
雨にたたかれ、口のなかに雨水がたまっていた。
雨が降ってなかったら助かったかもしれぬ。
医者がそう言っていたそうだ。
何とも、井伏鱒二の文章はすごいと思う。
なぜ私がこうした話を覚えているかというと、“口” なのだ。外村繁が運動場の向こうで笑っている黒い大きな口。雑木林で倒れている奥さんの、雨水が溜まっていた口。
どうにもその情景は、自分が見てきたようにある。それが井伏鱒二の文章だけから迫ってくるのである。
こういうことを書いていると、いろいろ思い出されてくる。三島由紀夫が『小説とは何か』でやはり文学、小説について書いていて、柳田國男の『遠野物語』の一篇を紹介している。
『遠野物語』は周知のとおり、岩手県遠野町に伝わる民話や民間伝承を蒐集したものだ。怪異譚が多い。三島はその中から第 22 節を紹介している。ちょっと長いが引用してみたい。ちなみに、旧漢字や旧仮名遣いは現代ふうに直す。
「佐々木氏の曾祖母年よりて死去せし時、
棺に取納め親族の者集まり来てその夜は一同座敷にて寝たり。
死者の娘にて乱心のため離縁せられたる婦人もまた中にありき。
喪の間は火の気を絶やすことを忌むが所の風なれば、
祖母と母の二人のみは、大なる囲炉裏の両側に坐り、
母人は傍らに炭籠を置き、おりおり炭を継ぎてありしに、
ふと裏口の方より足音来る者あるを見れば、
亡くなりし老女なり。
平生腰をかがみて衣物の裾の引きずるを、
三角に取上げて前に縫付けてありしが、
まざまざとその通りにて、縞目にも目覚えあり。
あなやと思う間も無く、二人の女の坐れる炉の脇を通り行くとて、
裾にて炭取にさわりしに、丸き炭取りなればくるくるとまわりたり。
母人は気丈の人なれば振り返りあとを見送りたれば、
親縁の人々の打臥したる座敷の方へ近より行くと思う程に、
かの狂女のけたたましき声にて、おばあさんが来たと叫びたり。
その余の人々はこの声に睡を覚ましただ打驚くばかりなりしといえり」
この中で私が、「あ、ここに小説があった」と三嘆これ久しゅうしたのは、
「裾にて炭取にさわりしに、丸き炭取りなればくるくるとまわりたり」
という件りである。
ここがこの短い怪異譚の焦点であり、日常性と怪異との疑いようのない接点である。
この一行のおかげで、わずか一頁の物語が、百枚二百枚の似非小説よりも、
はるかにみごとな小説になっており、人の心に永久に忘れがたい印象を残すのである。
そして、この一篇の分析が続く。
さすがに三島というのは律儀なのか、全文を引用して見せている。私が言いたいことはすべて三島が言っている。そういうことだ。
この話でまた思い出すのは、柳田國男の『山の人生』だ。これは山で暮らす人々にまつわる言い伝えをまとめたものだが、
マタギやアイヌ、サンカなどの言葉も出てくるやはり『遠野物語』に近い内容だ。その冒頭に柳田國男が見聞した、父親が子どもふたりを殺した話が載っている。
今では記憶している者が、私の外には一人もあるまい。
三十年あまり前、世間のひどく不景気であった年に、
西美濃の山の中で炭を焼く五十ばかりの男が、子供を二人まで、
鉞(まさかり)で斬り殺したことがあった。
女房はとくに死んで、あとには十三になる男の子が一人あった。
そこへどうした事情であったか、同じ歳くらいの小娘を貰ってきて、
山の炭焼小屋で一緒に育てていた。
その子たちの名前はもう私も忘れてしまった。
何としても炭は売れず、何度里へ降りても、いつも一合の米も手に入らなかった。
最後の日にも空手で戻ってきて、飢えきっている小さい者の顔を見るのがつらさに、
すっと小屋の奥へ入って昼寝をしてしまった。
眼がさめて見ると、小屋の口一ぱいに夕日がさしていた。
秋の末の事であったという。二人の子供がその日当りのところにしゃがんで、
しきりに何かしているので、
傍へ行って見たら一生懸命に仕事に使う大きな斧を磨いでいた。
お父(とう)、これでわしたちを殺してくれといったそうである。
そうして入口の材木を枕にして、二人ながら仰向けに寝たそうである。
それを見るとくらくらとして、前後の考えもなく二人の首を打ち落してしまった。
それで自分は死ぬことができなくて、やがて捕えられて牢に入れられた。
この親爺がもう六十近くなってから、特赦を受けて世の中へ出てきたのである。
そうしてそれからどうなったか、すぐにまた分らなくなってしまった。
私は仔細あってただ一度、この一件書類を読んで見たことがあるが、
今はすでにあの偉大なる人間苦の記録も、
どこかの長持の底で蝕ばみ朽ちつつあるであろう。
前時代的な話であるし、近代化以前、いやひょっとしたら、形を変えて今でも同じような悲劇はあるに違いない。
私が言いたいことはそういうことではなく、善悪、正邪はわからないが、何かしらどうしようもなく心を打つものがあり、それは何気ない短い文章からでも、否応なしに立ち上がってくるということなのだ。
そしてそれは文学作品、つまり文章で書かれたことである必要はなく、酒場にいるときや、通りを歩いているときに、ふと誰かの口から出たことであるかもしれない。
さきの子ども殺しの話でも、入口いっぱいに茜色の夕陽が射している光景が浮かばないだろうか。
何だか、小難しい話になってきたが、私はT田氏の話の続きをしたかったのだ。前置きが長くなり、何が本題かすぐわからなくなるのは私の悪いクセだ。最初の設定、目標からすぐ逸れてしまう。
また仕切り直しましょう。これから「おやすぴ」の収録もある。

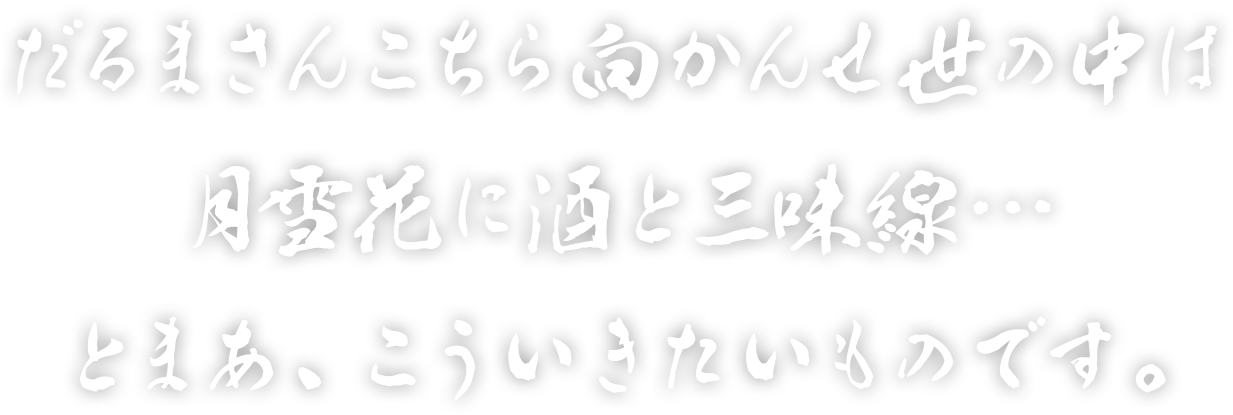
Commentコメント